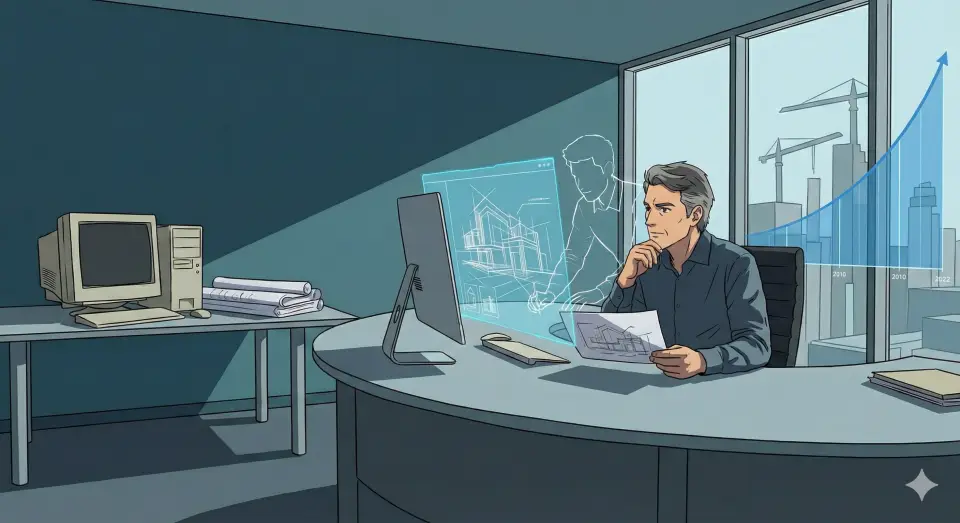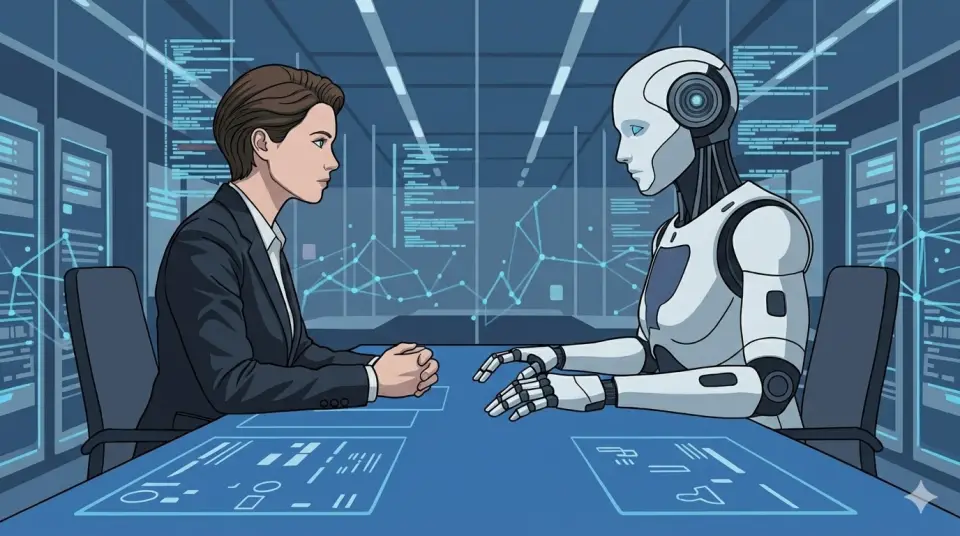ERPとは「システム導入」にあらず、「思想導入」である
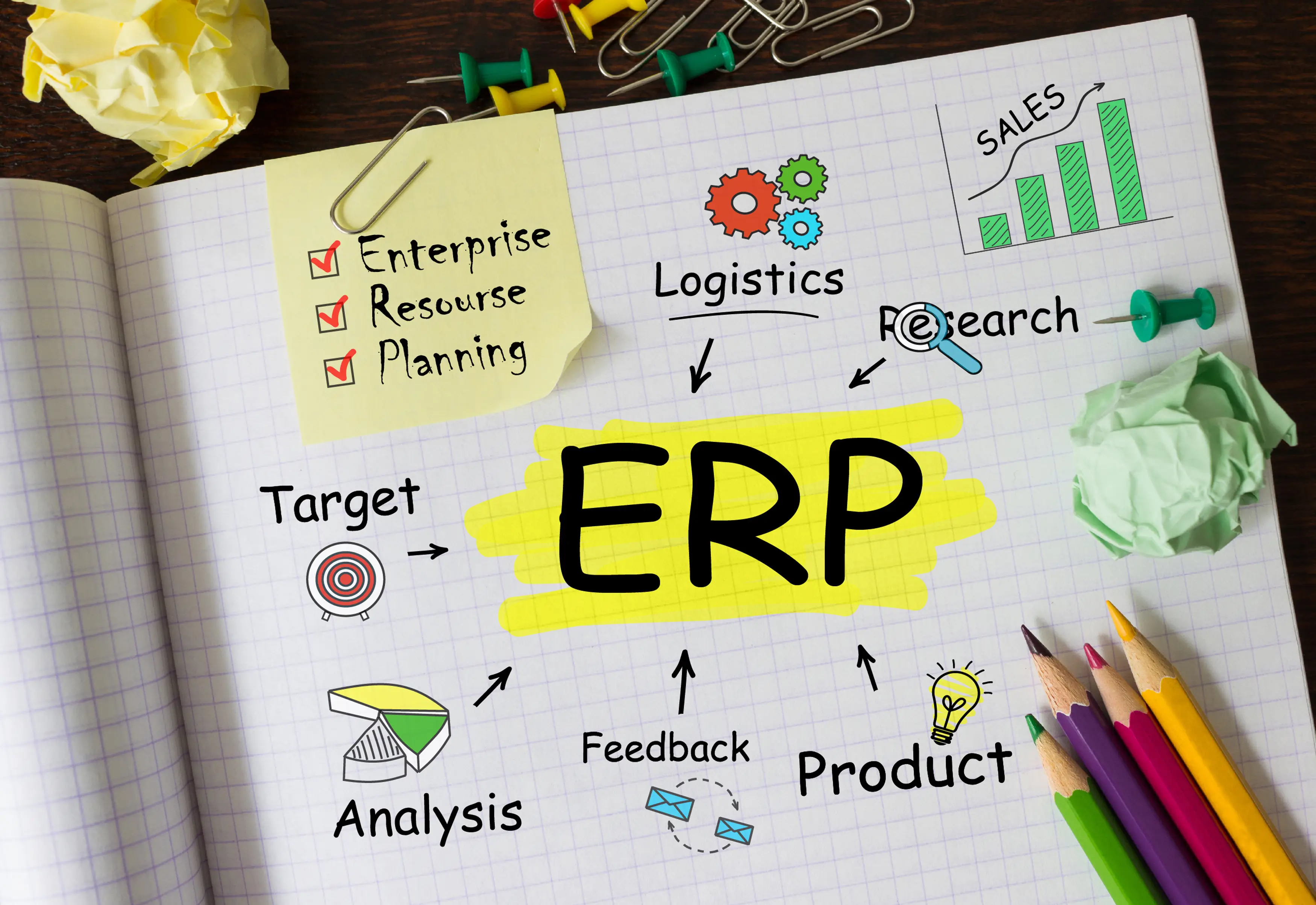
ERPと聞くと、多くの人がSAP、Oracle、Microsoftに代表される欧米製のパッケージシステムを真っ先に思い浮かべるでしょう。これらは企業の基幹業務を統合管理するために作られたパッケージであり、本来、スクラッチ開発よりも遥かに効率的で高品質なはずです。
しかし、残念ながらERPプロジェクトの成功率は驚くほど低いのが現状です。供給サイドであるコンサルティング会社やITベンダーも、日々「システム炎上」との戦いに疲弊しているのが実情ではないでしょうか。パッケージシステムなのに、なぜこれほどまでに導入が困難を極めるのでしょう。
【なぜERP導入は失敗するのか?】
結論から言えば、ERP導入は情報システムの導入に違いありません。ですが、もしそれだけなら、もっとスムーズに進むはずです。導入がこれほど難しい最大の原因は、ユーザー側が「ERPという思想」の導入にコミットしておらず、供給側がその変革をリードできていないという、双方の課題にあります。
私たちは、なぜ単なる「基幹システムパッケージ」ではなく「ERPパッケージ」と呼ぶのか、その原点から理解しなくてはなりません。ERPについて語られるとき、次のようなキーワードがよく登場します。
- “見せる化”から“見える化”へ
- 部門最適から全体最適へ
- コア・コンピタンスへの注力
- マネジメント改革
これらは提案書で頻繁に目にする、至極真っ当な言葉です。しかし、そのほとんどがユーザーとベンダー双方にとって、単なる「スローガン」で終わってしまっているのではないでしょうか。
「そんなことは分かっている。それでも、うまくいかないんだ!」
そんな声が聞こえてきそうです。ですが、私たちは本当にその本質を理解できているのでしょうか。
【ERPの「思想」を具体的にイメージする】
ERPを導入する上で、システムの実装以上に困難な課題があります。それは、ERPの思想に業務を適合させるための、マネジメント体制の構築と、それを実現するための業務ルールの再設計です。
2024年5月に経済産業省が公表した資料の中に、この問題を的確に表現した資料があります。
※引用:経済産業省「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」より抜粋
ここに登場する「バケツリレー式経営」とは、まさに本質を捉えた比喩です。これは、経営層が「情報を持ってこい」と指示を出し、現場がリレー方式で報告を上げていく、多くの日本企業に見られる旧来のマネジメントスタイルを指します。
ERPが目指すのは、このスタイルからの脱却です。経営サイドが「水を持ってこい」と待つのではなく、自ら「水を汲みに行く」スタイルへ変革しなければなりません。つまり、付加価値の高い「情報」を、経営層が必要なタイミングで自ら取得し、活用するスタイルへの改革が求められるのです。
これを実現するには、システムにはリアルタイム性が不可欠ですし、現場の担当者も、そのスピードに対応できる業務プロセスへと変わらなければなりません。これがどれほど大規模な業務改革であり、システムの実装はその次の課題に過ぎないことが、お分かりいただけるかと思います。
【供給側の役割と責任】
数億円を投じたERPが、単なる高価な計算機と化してしまう原因の多くは、供給ベンダー側のERPに対する理解不足にあると言っても過言ではありません。
いまだに多くのプロジェクトでは、顧客の要求とERPの機能を比較し、Fitすれば標準機能、Gapがあればアドオン開発、という「Fit & Gap分析」が主流です。しかし、このやり方だけでは、ERPが本来もたらすはずの業務改革は決して実現できません。
供給ベンダーは、まず自らがERPの思想を深く理解し、単なる機能説明ではなく、その背景にある「思想」を顧客に丁寧に説明すべきです。
例えば、ERPの受注登録画面にあるエラーチェック機能について、単に「この項目は必須なので、登録時に必ず入力してください」と説明したとします。これでは、ユーザーは「面倒なルールが増えた」と捉えるだけで終わってしまいます。
そうではなく、次のようにリードすべきです。 「この機能は、受注という『契約』を法的に、またビジネス的に成立させるために最低限必要な情報を担保するためのものです。もし、この段階で情報が揃わないのであれば、それは契約プロセスそのものに課題があるのかもしれません。どうすれば迅速に情報を集められるか、一緒に議論しませんか?」
このように、システムファンクションの説明を「思想」にまで落とし込み、顧客の業務改革をリードしていくことこそ、供給ベンダーが果たすべき真の役割なのです。
【結論:変革の主役はマネジメント層】
突き詰めれば、「誰がその情報を利活用するのか?」という視点がすべてです。そして、その活用者である経営層や管理職自身の、意識と業務双方の改革が不可欠なのです。
ERP導入を決断したからには、経営者、マネジメント層、管理者が「自社にとって本当に必要な情報は何か」「その情報をどう活用すれば企業が成長できるのか」を真剣に考え抜く必要があります。ERPパッケージは、あくまでその目的を実現するための情報基盤に過ぎないのです。
【供給側の重い責任と自戒】
先に述べた通り、ERPプロジェクトに参画するコンサルタントやベンダーには、ユーザーのマネジメント層をリードするという、非常に難易度の高い役割が求められます。
自戒を込めて言えば、この役割を果たせている供給ベンダーは、残念ながら極めて少ないのが実情です。これは、私たちIT業界全体が取り組むべき最重要課題と言えるでしょう。この状況を放置すれば、「ERP」というだけで高単価なコンサルタントが価値を提供できない、という歪んだ業界構造が定着してしまいかねません。ERPに関わるすべての者が、その本質と自らの責任を再認識すべき時が来ています。
お問い合わせください